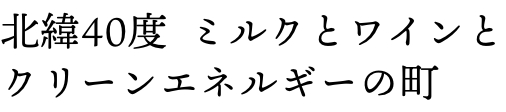公開日 2025年08月01日
健康保険税の概要
国民健康保険(国保)制度は、相互扶助の精神に基づき、加入者の病気やけがをした際などに保険給付を行うことを目的とした制度です。
その財源は、皆さんが納める国民健康保険税(国保税)と、国からの交付金などで成り立っています。
世帯主が納税義務者となります
国保税は、世帯主に課税されます。
世帯主が国保加入者でなくとも、世帯内に国保加入者がいる場合は、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務を負うことになります(納税通知書などの書類も世帯主宛てに送付されます)。
国民健康保険税の税額計算
国保税は、国保加入者ごとの「基礎課税分」、「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」をそれぞれ算出して合計した金額が、世帯の1年間(毎年4月から翌年3月まで)の税額となります。
「基礎課税分」と「後期高齢者支援金分」は国保加入者全員に課税されますが「介護納付金分」は満40歳以上65歳未満の国保加入者のみ課税されます。
税率
| 税率・税額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | |
| (前年中の総所得額等-43万円)×税率 | 固定資産税額×税率 | 国保加入者一人当たり | 一世帯当たり | |
| 基礎課税分 (課税限度額66万円) |
6.8% | 22.2% | 18,000円 | 24,800円 |
| 後期高齢者支援金分 (課税限度額26万円) |
3.1% | 9.7% | 7,700円 | 10,600円 |
| 介護納付金分 (課税限度額17万円) |
2.4% | 10.0% | 9,000円 | 9,100円 |
※所得割と均等割の税額は、国保加入者ごとに算出します。
保険料決定時期
前年の所得が6月に確定するため、その後保険税を算定し、7月中旬に保険税決定通知書を発送します。年度途中で加入者の異動などがあった場合は、国保資格手続きの翌月に決定(更正)通知書を発送します。
※葛巻町外から転入された方については、前住所地に所得の照会をした後に税額を計算するため、後から所得割が課税される場合があります。
確定申告・住民税申告をしていない場合
国民健康保険税の算出や軽減判定については、住民税申告(確定申告)による所得を用います。
世帯主と国保加入者の所得が確定していない場合、正確な税額計算ができないだけでなく、軽減の措置を受けることができません。収入がない方であっても忘れずに住民税申告をしてください。
納付方法
普通徴収による納付(口座振替・納付書払い)
納付月は、7月~翌年2月(年8回払い)です。
年度途中の加入者などの異動で、納付開始月、最終月、納付回数が異なることがあります。
| 普通徴収の納期限 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 翌年1月末 | 翌年2月末 |
※納期限が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。
口座振替
取扱金融機関は、岩手銀行、盛岡信用金庫、新岩手農協、ゆうちょ銀行です。一度、口座振替の手続きをすると毎年忘れることなく納付することができます。
口座振替の申し込みは、金融機関で受け付けています。申し込みの際は預金通帳、通帳印、納付書をお持ちください。なお、金融機関との処理の都合から口座振替に切り替えるまでに、1カ月ほどかかります。納期限の1カ月前までに手続きをお願いします。
※国保税の納税義務者は「世帯主」です。世帯主の変更や世帯分離・合併などによる申し込みの際は、ご留意ください。
※国保脱退や世帯主・加入者の変更などの際は、振替口座の登録内容を確認の上、変更・解約などの手続きをお願いします。
※残高不足などで口座振替ができない時は、納付書を送付しますので確認の上、納付してください。
納付書払い
住民会計課窓口や納付書の裏面に記載している金融機関、コンビニのほか、スマートフォンアプリを使った電子マネーで納付することができます。また、令和5年度より納付書に「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印字されたことで、全国のeL-QR対応金融機関での納付や納付書裏面に記載の決済アプリからQRコードを読み取ることで納付できます。
※納期限を過ぎたものは、金融機関で納付してください。
特別徴収による納付(世帯主の年金から天引き)
年金から特別徴収する条件は、国民健康保険に加入している方で、次の1から3までの全てに該当する場合、支給される年金から国保税が差し引き(特別徴収)されます。
- 世帯主が国保加入者(国保資格のない世帯主を除く)であること
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる世帯主の年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えていないこと
※年度内に75歳に到達する加入者がいる世帯の場合、その年度は特別徴収されません。
※世帯状況の変化により税額が増加した場合、納付方法が変更となる場合があります(変更になった都度通知します)。
| 特別徴収の納付月 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
※年金から国保税が特別徴収される方も、手続きをすることで口座振替に変更できます。
保険料の算定
年間の保険税額は7月に決定するため、前年度から引き続き年金から特別徴収されている方は、前年度2月の支払額と同じ額を4、6、8月の年金支給月にそれぞれ仮徴収します。
7月に決定した年税額の過不足分を10、12、翌年2月の本徴収で調整します。よって、仮徴収と本徴収では徴収額が異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ
住民会計課 TEL 0195-65-8994